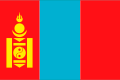センターだより
プロジェクトワーク発表会
2017/04/24
4月21日、1年生のプロジェクトワーク発表会が行われました。
テレビ会議システムを利用して、カンボジアセンターの先生方、ウズベキスタンセンターのみなさん、ホーチミンセンターの学生さん、名古屋大学留学中の卒業生、名古屋大学および首都大学東京で日本語教育を専攻している大学院生の方々が世界各国から発表を見てくれました。
発表のテーマは以下の4つ
・モンゴルのらくだ
・モンゴルの女子学生
・モンゴルの乳製品
・モンゴルの遊び
本番前日までPower Pointのスライドを修正したり、発表練習をしたりとバタバタでしたが、なんとか無事終了し、学生たちもこのプロジェクトワークでまた一つ自信とやる気を高めたようでした。



お忙しい中参加してくださったみなさま、どうもありがとございました!
たこやきパーティー
2017/04/21
プロジェクトワーク発表会の打ち上げと称して、タコ焼きパーティーを行いました。
「タコ焼き」と言っても、海のない国モンゴルの人々にとってタコは、8本足の虫なのかなんなのかわからない不気味な生物でしかないらしく、食べることも触ることも見ることも怖いという学生続出・・・
結局、学生用「タコ焼き」の中身はチーズとハムになりましたが、それはとてもおいしかったらしく、自分たちでくるくると転がしきれいに丸く作れるまでになりました。
ちなみに、「タコ」の入った「タコ焼き」は教員がすべておいしく食べましたが、「タコ」だと言われて市場で買ったそれは結局「ゲソ」でした。まあ、店員さんにとっても、タコもイカも足がやたら多い不気味な海の生物という意味では同じなのでしょう。
留学短報 Apr 2017
2017/04/11
京都大学に留学中のツェベルマーさんからお便りが届きました。カフェでお勉強とは、ツェベルマーさんもすっかり日本の女子大生になりましたね。
——————————————————————————————————
皆さん、ご無沙汰しております。お元気ですか。桜の京都より今月の報告を申し上げたいと思います。2ヶ月に渡る長い春休みがあっという間に終わってしまい、4月10日から新学期が始まりました。さて、今回の報告では、まず季節のニュースとそれから、学生限定の「知るカフェ」というところについてお伝えしたいと思います。
まず、日本の春は桜の季節です。ですが、桜が咲く時間は非常に短く、一週間弱で終わってしまいます。開花する時期が場所によって違いますが、京都の場合、4月の下旬から中旬に開花しました。この前、大阪の産経新聞社に訪問したことを申し上げましたが、その際、一人の記者が「季節のニュースを書くのが好きだ」と言っていました。私は、内心「それの何が面白いんだろう?」と思っていました。しかし、季節のニュースがとても大事なのだということが実感しました。なぜなら、桜は開花する日にちが、場所によっても年によっても、違ってきます。そんな中で「4月7日、蹴上で桜が開花しはじめました。見頃です。」というニュースと綺麗な桜の写真があれば、それを手掛かりに無駄足せず花見を楽しめるということです。

次は、私が週に2、3回行く「知るカフェ」というところの紹介をしたいと思います。「知るカフェ」は、美味しいコーヒーを無料で飲める大学生限定のカフェです。1日に何回入っても無料で飲み物を飲めます。引き続き飲む場合は、100円を払います。普通のお店でコーヒーなら300円から400円です。さて、皆さんには、きっと「なぜ無料なのでしょう?」という疑問が生じたと思います。「知るカフェ」では、もちろん勉強はできますが、他にも色々な会社からのイベントが行われます。つまり、優秀な学生を雇いたいという会社といい会社に就職したいという学生が出会う場所でもあるわけです。日本の大学生は卒業する前に就職活動を始めるので、卒業する前に色々な会社と接触してみた上で自分にふさわしい職場を決めるのにも役に立つのではないかと思います。では、学生の代わりに誰がコーヒー代を払っているのでしょうか。答えは、多くのスポンサー企業たちです。とてもありがたく思っています。居心地が良く、お金も払わないので気楽に利用することができます。1年間だけの留学生である私も日本人大学生と代わりなくサービスをしてもらっています。
皆さんも、日本に来たらぜひ行ってみてくださいね。店員さんも同じ学生なので、とても親切に対応してくれます。
では、また来月の報告でお会いしましよう。
留学短報 Mar 2017
2017/03/29
京都大学留学中のツェベルマーさんからお便りがとどきました。
———————————————————————————————————- 皆さん、こんにちは。中間テストが始まり、みんなお忙しいかと思いますが、今月の報告を申し上げたいと思います。今月は、日研生のみんなで岐阜県の高山市白川郷、飛騨高山に見学旅行に行ってきました。大雪が積もっていて、北海道みたいでした。 白川郷は1995年に「人類の歴史上重要な時代例証する或る形式の建造物、建築物群技術の集積、または、景観の顕著な例」として世界文化遺産に登録されており、今回はその中心となる合掌造り集落群を紹介させていただきました。
まず、築後約300年が経過した今も生活が営まれ続けている合掌では今のような核家族ではなく、複合家族で住んでいたそうです。そのため、合掌の中は非常に大きいです。合掌造りの技術は優れていることはもちろんだが、ここで皆さんに注目していただきたいのは、白川郷の集落での生活において一番大事なことは、個々の家の助け合いと協力です。
これこそ、合掌造り集落の存在の命といっても過言ではないでしょう。集落が山間部に位置し、寒い冬には雪に閉ざされる厳しい自然条件に置かれた白川村では、家が単独で生活を維持するのは大変困難だからです。そのため、年間を通したさまざまな暮らしの場面で共同や互助が必要とされ、白川村ならではの相互扶助の関係が築かれてきたそうです。自然と共に生きる昔ながらの生活について少しでも知ることができたように思います。
▲岐阜県高山市白川郷集落群
さて、その後は読書に日々が続き、部屋の中で引きこもっていましたが、ついに寮から飛び出してチャリティーコンサートを見に行きました。実は、女性の地位向上・教育を柱として様々な諸問題に取り組む国際ソロプチミスト京都―東山クラブからの招待で行ってみました。とても楽しかったです。
モンゴルでの毎日は、次々と出される宿題やレポート、試験準備で過ごされ、芸術への関心は忘れられていたように思います。私は、小さい頃から学校以外にダンスやスポーツなどに挑戦したことがまったくなく、静かで平和な日々を送ることだけに最善を尽くしていました。しかし、やっと気づきました。できるか、できないかは関係なく、とりあえず何でも挑戦してみることが大事なのだということに。ですので、今回はコンサート中に二人の客にみんなの前で指揮者をやってみるチャンスをくれました。私は、ためらうことなく手を上げました。うまくできませんでしたが、良かったと思います。指揮者は手を動かしているだけで、苦労してないように見えるのだが演奏において一番大事な仕事をしているということが後で撮られた自分の下手な演奏を聞いて実感しました。
皆さんも、できるかな、大丈夫かななどと思うより、何でもやってみてください。結論はやる前にではなく、やってみてからにしてくださいね。では、また来月の報告でお会いしましょう。

日本語教師体験
2017/03/23
3月8~21日まで、名古屋大学大学院で日本語教育を専攻している大学院生の末松さんが日本語教師体験でモンゴルセンターに来てくれました。
モンゴルセンターでの授業を担当するだけでなく、近隣の日本語教育機関への見学やモンゴルセンターの10周年記念式典、日本語教師会のシンポジウムなどもあり、非常に慌ただしかったのですが、全ての学年の授業に入って熱心に教えてくれ、学生たちにとっても教職員にとっても刺激的で楽しい2週間となりました。
末松さん、ありがとうございました!